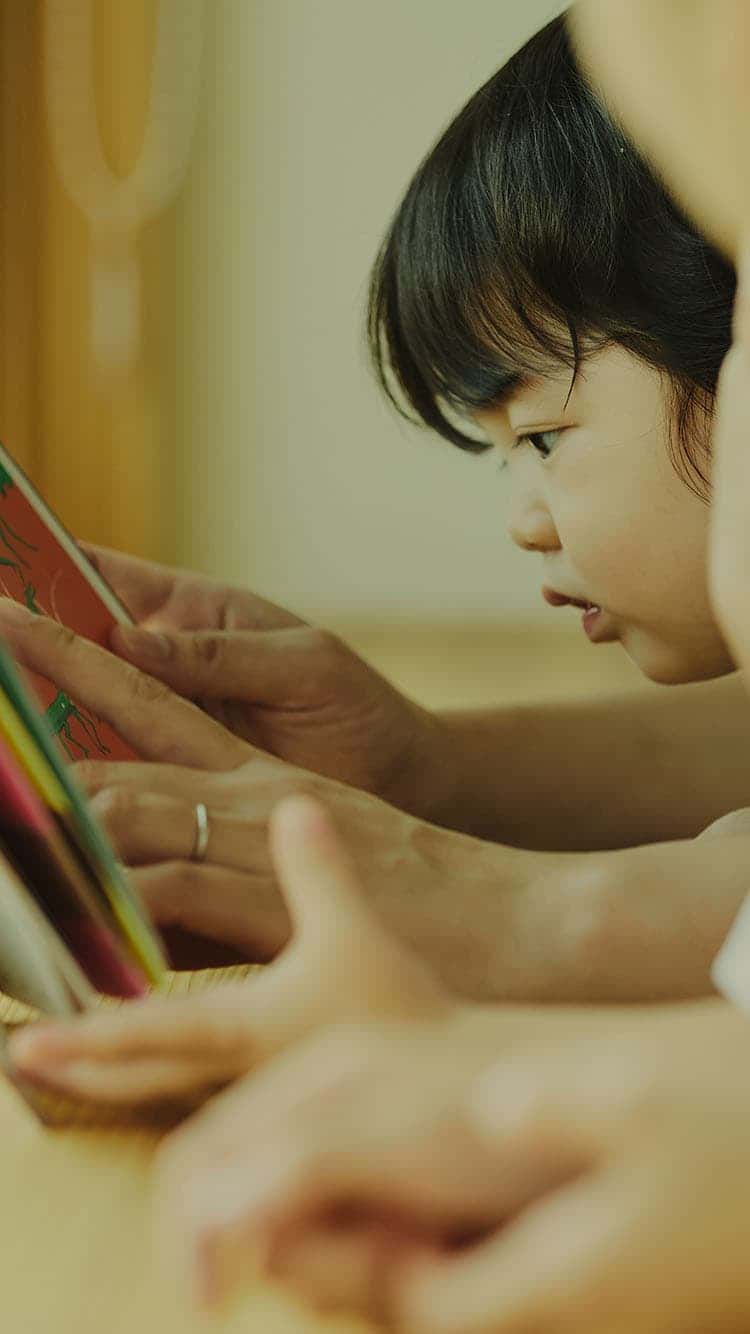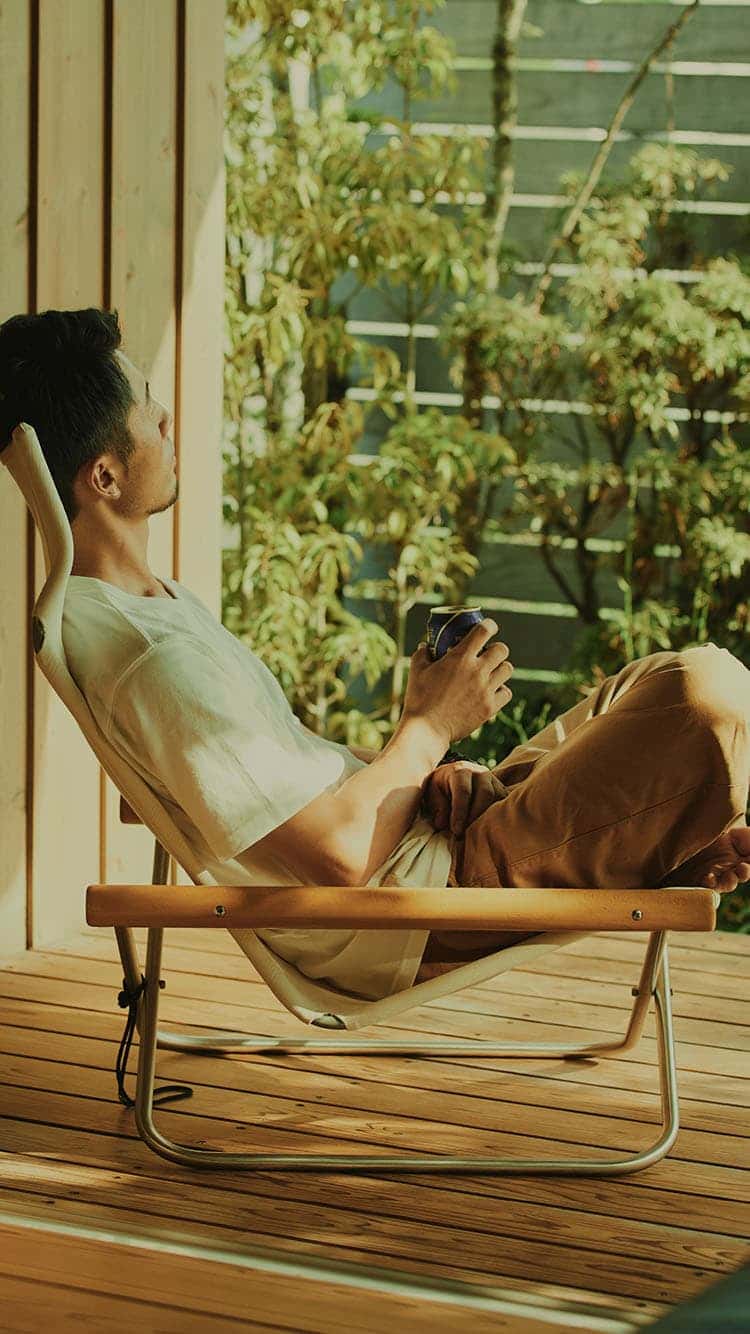「屋敷林物件をどうにかできないか」 一件の相談から始まった新たな暮らしのプロジェクト

地域に根付いた散居集落の景色から着想を得て、「広い敷地に散らばって暮らしを営む」という新たな暮らしを創造していくsun-kyoの分譲住宅。2025年7月に全4棟のオープンを予定し、現在建設が進められています。
富山県中新川郡立山町で始まった、MAEKAWAグループが手がけるsun-kyoプロジェクト。その始まりから、プロジェクトが始動するまでのストーリーをたどります。
つながりが生んだ一件の相談
2022年の暮れ頃、前川建築のグループ会社である株式会社コノカの南部さんに、地元の不動産会社から相談の連絡がありました。内容は「立山町にある屋敷林物件をどうにかできないだろうか」というもの。無人化した屋敷林は再生・維持管理が難しく、広い敷地がありながら買い手のつきにくい物件です。
そこで、以前に自宅の外構工事をniwasonoに依頼されたことがある不動産会社の方が「屋敷林物件の相談をするならMAEKAWAグループに」と、南部さんに連絡したのだといいます。
屋敷林を継承する方法の模索
物件の話を聞いた前川社長は屋敷林再生への思いを抱き、まずはあるものをできるだけ多く残して利用できないかと考え、MAEKAWAグループで屋敷林物件の調査を開始しました。
敷地内に立っていた空き家は築年数が40〜50年になり、ちょうど新建材が普及してきた時代の建物であることが判明。資産価値がないことから改修はせずに解体することを決め、そこから屋敷林の新たな活用方法の模索が始まります。
できるだけ環境を残し、継承していく活用方法を導き出すために、前川社長は町の工務店ネットで以前からつながりのあった趙海光さんに相談することに。
趙さんは、町の工務店ネットと共同で「現代町家」という家づくりを展開している一級建築士。自ら構築した設計システムをもとに、町の工務店ネットに参加している日本各地の工務店と協力して、地域ならではの家づくり、そして戸建て住宅団地を数多く実現しています。

1948年、青森県生まれ。1972年、法政大学工学部建築学科卒業。1980年に株式会社ぷらん・にじゅういちを設立。1990年代には台形集成材を使用する一連の木造住宅「台形集成材の家」を設計。一貫して国産材を使用する現代型木造住宅の設計を続け、建築雑誌へ木造住宅についての論考を多数発表。国産材の開発と普及に努める。2007年以降は「町の工務店ネット」と共同で、日本の町家建築に学んだスタンダードな木造住宅を目指す「現代町家」シリーズに取り組んでいる。



前川社長は、2023年3月に行われた町の工務店ネットの総会で趙さんに会い、屋敷林物件の活用方法について相談を持ちかけました。
敷地の現状や立地について説明し終えると、「これは、すごくいい場所になるよ」と趙さん。その一言を聞いて、前川社長はプロジェクトの発足を即断したと言います。
新たな暮らしを創造するプラン
プロジェクトの発足からしばらくして、趙さんから1つのプランが提案されました。それは「敷地内に複数の家を建て、豊かな木々で住宅同士の境目をゆるやかに設計する」というもの。
そして、屋敷林を新たな形で再生、活用する方法として「外から取り込まず、中から出さない」「土盛をせずに現状のまま造成し、傾斜を利用して建物を配置する」「今ある環境をなるべく残しながら、屋敷林を構成している木々を針葉樹から広葉樹に変え、明るい環境にしていく」ことが、プランに盛り込まれていました。

前川社長は「提案を聞いた時点でプランの成功をイメージできた」と言います。そして同じように、MAEKAWAグループの皆さんもプランに賛同。
初回の提案でプランの大枠が決定し、屋敷林を新しい形で継承していくためのsun-kyoプロジェクトが始動しました。