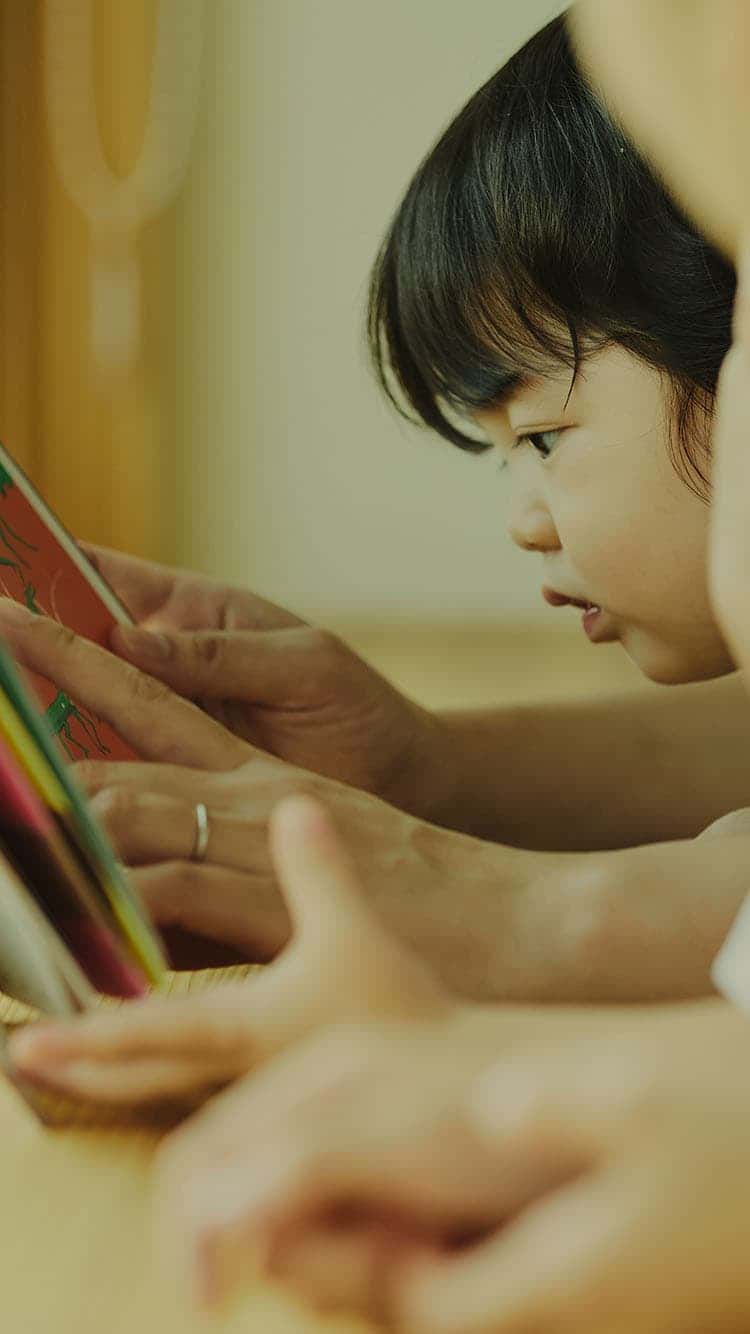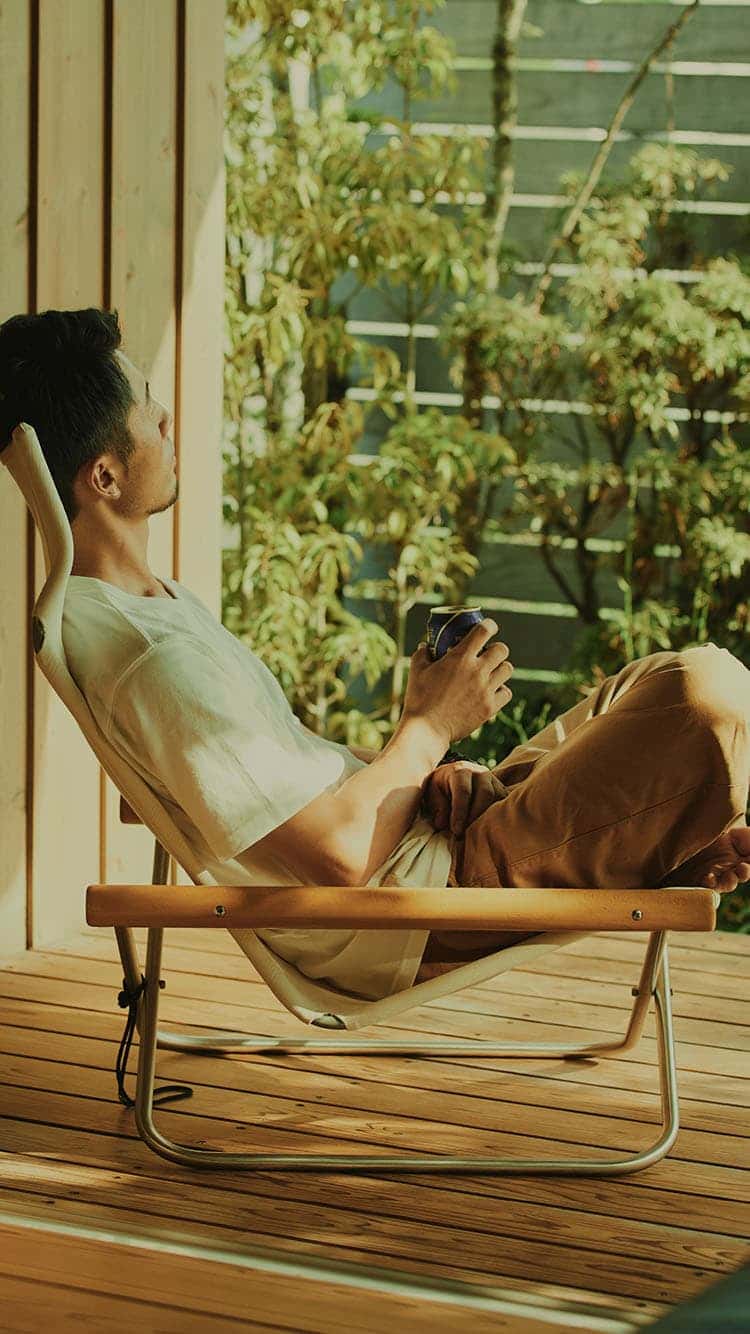【風景のロングパス_2】 常願寺川
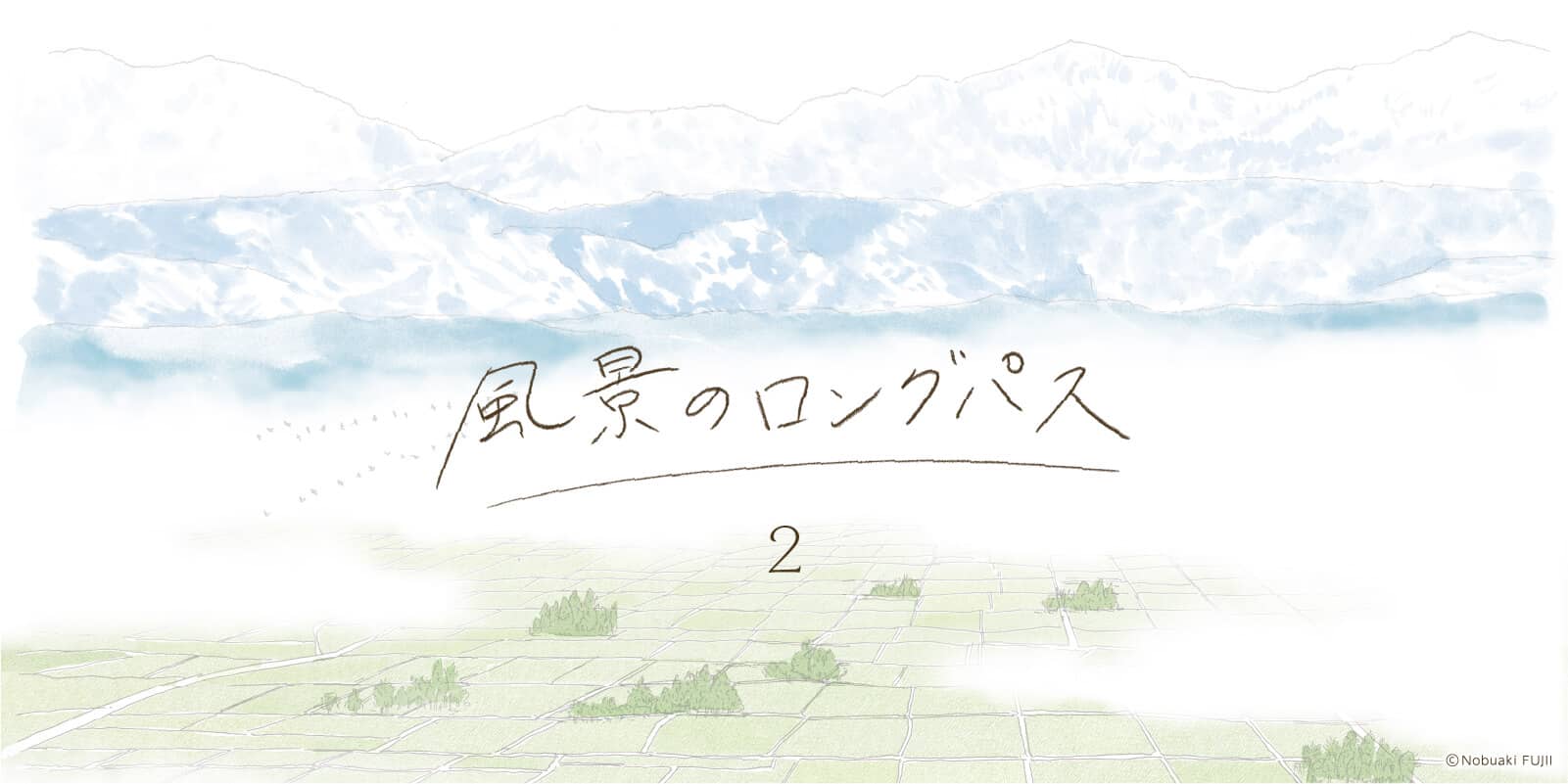
sun-kyoプロジェクト・設計チームの趙 海光さんによるエッセイを、全12回に渡ってお届けします。
タイトルである“風景のロングパス”には「遠い先の誰かに、この風景をロングパスしよう」というこのプロジェクトへの想いが込められています。
常願寺川
立山町に行ったのは、こんな相談があったからでした。「荒れた屋敷林と空き家があるのだけれど、その活かし方を考えてくれませんか?」
「おお、これは!」と心が躍ったのは、私は「家を造るとはつまり環境を造ること」と考えてきたからで、「荒れた屋敷林」という言葉が私の胸を怪しく揺さぶったのです。ただ、東京で仕事をしている私には「屋敷林」がいかなるものか具体的な像が浮かびません。荒れた屋敷林?空き家?‥‥頭に浮かぶのは鬱蒼とした竹藪に包まれた荒屋(あばらや)のイメージでした。
さてしかし誘われるままに北陸新幹線に乗って富山駅へ。そして駅から車で西へ向かうと、やがて真っ正面に立山連峰が圧倒的な姿を現します。その屏風のような山並みに向かって30分も走ったでしょうか、大きな川を渡ったところに目指す屋敷林がありました。
そのとき渡った川の名前は「常願寺川」。後日、調べるにつれてこの川が立山町の「散居風景」の鍵になっていることがわかってくるのですけれど、この時はまだ名前も知りませんでした。


1948年、青森県生まれ。1972年、法政大学工学部建築学科卒業。1980年に株式会社ぷらん・にじゅういちを設立。1990年代には台形集成材を使用する一連の木造住宅「台形集成材の家」を設計。一貫して国産材を使用する現代型木造住宅の設計を続け、建築雑誌へ木造住宅についての論考を多数発表。国産材の開発と普及に努める。2007年以降は「町の工務店ネット」と共同で、日本の町家建築に学んだスタンダードな木造住宅を目指す「現代町家」シリーズに取り組んでいる。