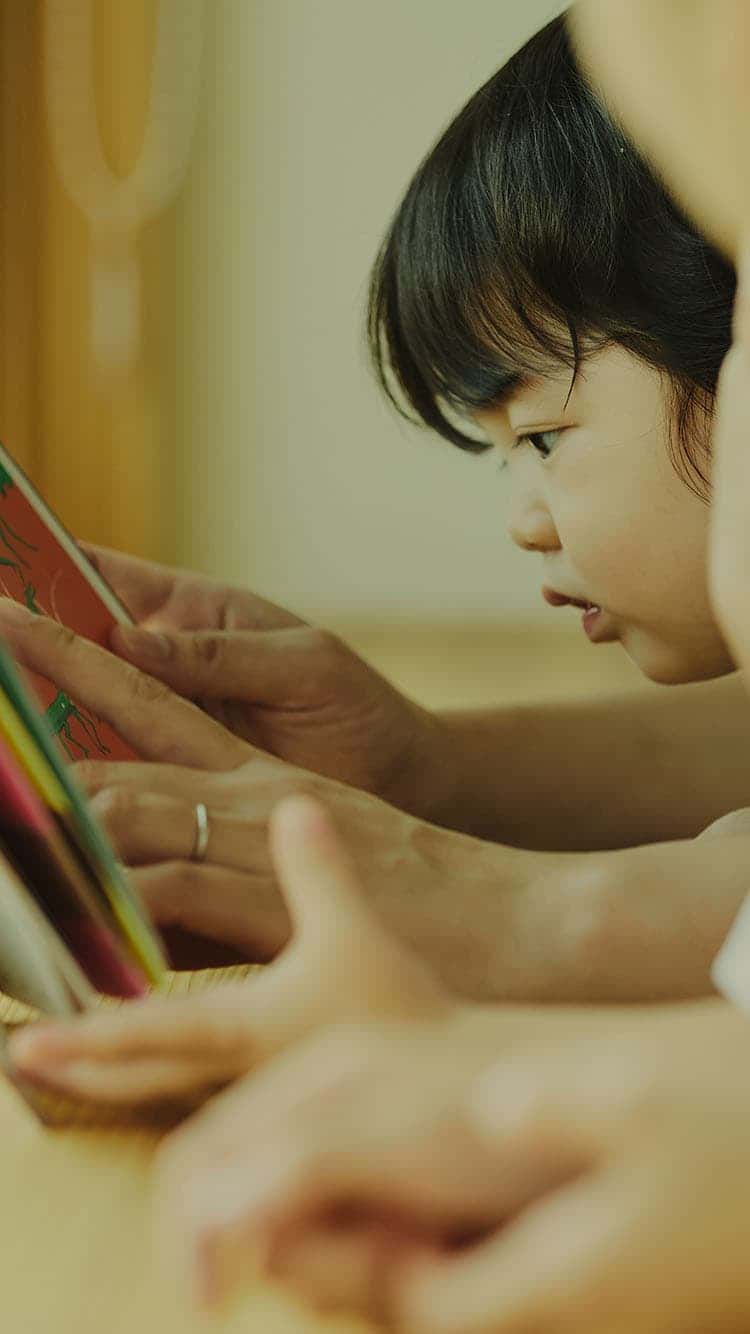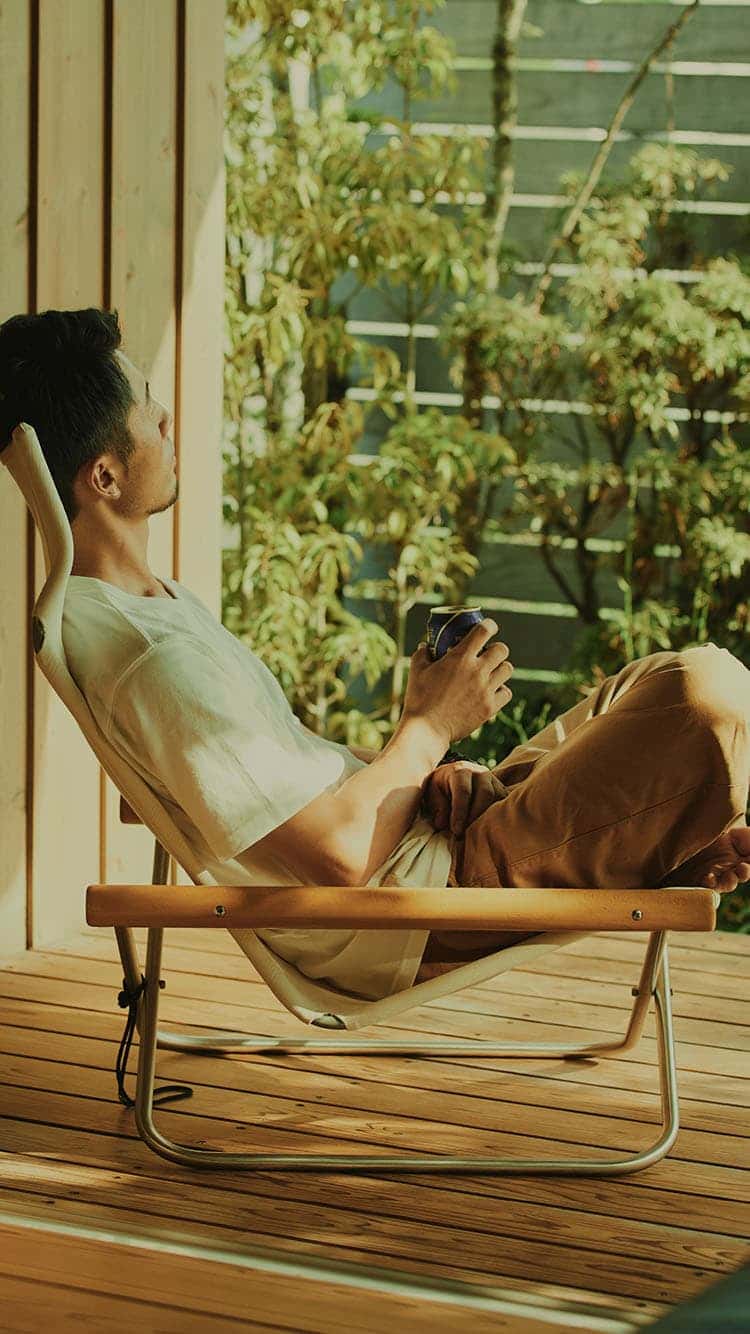【風景のロングパス_9】防風林から雑木林へ

sun-kyoプロジェクト・設計チームの趙 海光さんによるエッセイを、全12回に渡ってお届けします。
タイトルである“風景のロングパス”には「遠い先の誰かに、この風景をロングパスしよう」というこのプロジェクトへの想いが込められています。
防風林から雑木林へ
さて「伐るのか、残すのか?」という話(第7話)に戻りましょう。私たちが下した決断は「伐る」でした。
⻄側に⼀列に並んだ杉の⾼⽊は全部で5本。この屋敷林の象徴みたいな、⾼さ20m近い樹列です。それを伐るわけですから、なんてバチ当たりな!と我ながら悩みました。
しかし、それでも伐るという決断に⾄ったのは、この屋敷林を「防⾵」という重荷から解放したかったからです。 防⾵林としてではなくて、この屋敷林をもっと⾥⼭的な機能を強めた雑⽊林にしたいと思いました。
「⾥⼭的な機能を強める」とはつまり保⽔⼒を⾼め、植物の種類を増やし、トンボや蝶を呼び、カエルが住めるようにするということです。
杉の⾼⽊に覆われていた暗い地⾯に⽇射を⼊れ、密になったところの中低⽊を間引き、下草がちゃんと育つ環境をつくって‥‥堀さんたち造園チームが現場の植⽣を少しづつ整理していったところ、結局残ったのはエノキ、タラヨウ、サクラ、ハクモクレン、イヌシデなど、全部で19本の⽊々でした。


1948年、青森県生まれ。1972年、法政大学工学部建築学科卒業。1980年に株式会社ぷらん・にじゅういちを設立。1990年代には台形集成材を使用する一連の木造住宅「台形集成材の家」を設計。一貫して国産材を使用する現代型木造住宅の設計を続け、建築雑誌へ木造住宅についての論考を多数発表。国産材の開発と普及に努める。2007年以降は「町の工務店ネット」と共同で、日本の町家建築に学んだスタンダードな木造住宅を目指す「現代町家」シリーズに取り組んでいる。